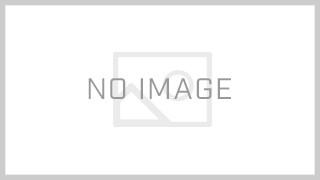「学ぶ」という行為にも、守・破・離の三段階があるように思う。
学びの「守」とは、無条件に受け入れること。あえて自分を、教えられた型にあてはめてしまう行為だ。
学校の九九や、社会人のエチケット・マナー、職場のマニュアルなどだ。この段階で要求される学びの水準は明快だ。それは、「いつでもそれが出来る、使えるようにすること。」である。
このレベルはもう卒業した、と思わないでほしい。すでに50才になったあなたも、ある学習分野では、いまでも「守」でなければならないことがあるはずだ。
学びの「破」とは、個性を要求される段階だ。あなたらしさ、オリジナルが求められる。創意工夫と知恵によって、あなたの個性や人間性を仕事に加味していくのだ。
あなた独自の体験を通して気づいたことと、以前から知識として知っていたものとが結合する瞬間がある。それが冒頭のドリスがいう、「突然新しく見える」瞬間であり、真の学習だ。これが日々ある人は毎日新しい。
学びの「離」とは、あなたが何かの標準になることだ。
「ハンフリーボガードにあこがれ、ボガードを真似、ボガードを演じ続けるうちに、気づいてみたらダスティン・ホフマンになっていた。」
これは、ホフマン本人の言葉だ。これが「離」の一面だ。
古くからそれはある。だが、新しいアイデアが加わることで、まったく別の価値が生まれることがある。たとえば、文字を書くために発明された「紙」。
中国で最初に作られたのは、後漢時代の西暦100年頃だという。それから紙は様々な用途に使われ、19世紀後半になって米国でトイレットペーパーなるものが発明された。
これまでにも紙の存在を知っていながら、それをトイレのロール紙に使うまでには何と1900年を要している。これが、学ぶということの一面だ。
1687年、イギリスのニュートンは、その論文のなかで「距離の2乗に反比例する力として重力が存在する」と述べた。
いわゆる『万有引力』の発見である。これは、リンゴが木から落ちるのを偶然見ていてひらめいたものだという。人類がリンゴ落下を目撃してから何千年たっただろう。これが、学ぶということの一面だ。
ずっと前から紙を知り、リンゴ落下を知っていた。だが、それが、他の価値ある何かに応用できることを知るには、「突然新しく見える」瞬間を必要とする。